
AIに茨城県で評判の良い社労士トップ5を聞いてみた
AIの回答は残念ながら全くアテにならず ChatGPT、Gemini、Cladeに「茨城県で評判の良い社会保険労務士トップ5をご紹介いただけますか。」と聞いて ...
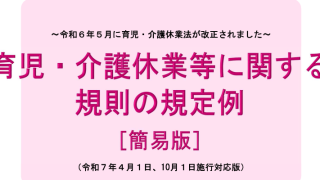
育児・介護休業等規程の規定例「2025簡易版」公表
育児・介護休業等規程2025法改正の規定例と改正点 2024年11月1日、厚生労働省が「育児・介護休業等に関する規則の規定例(2025年対応)[簡易版]」を公 ...
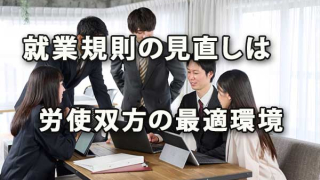
就業規則は変化に対応させ労使双方の最適環境を
公正な労働環境を確保するため時代の変化に合わせ適切に 就業規則は、雇用関係の基本ルールを定めた重要な文書です。近年、働き方改革や法改正の影響を受け、就業規則の ...
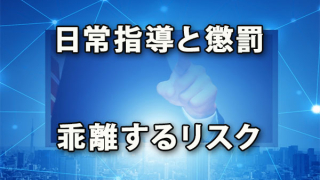
日常の指導と懲罰が乖離する危険性防止に言行一致
日常の指導と懲罰が乖離すると組織の崩壊も 就業上のルールに対する日常の指導と懲罰が乖離している場合、組織にとって複数の不具合やリスクが生じる可能性があります。 ...
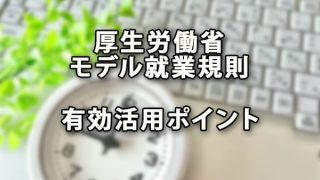
厚生労働省モデル就業規則活用の注意ポイント
モデル就業規則や就業規則ひな形使用の注意点 厚生労働省はじめ、ひな形の就業規則を単に加工して使用する場合、以下のようなリスクが考えられます。 企業固有の事情に ...
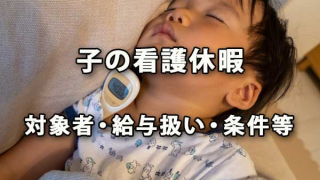
子の看護休暇の内容(対象者や給与の扱い、条件等)
子の看護休暇は時季変更権が無く欠勤でもない 子の看護休暇は、子育て世代を支援する制度として、企業に導入が義務付けられている休暇制度のことです。子育てをしながら ...
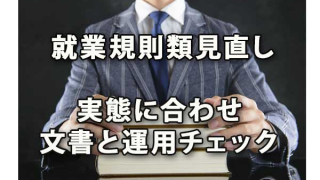
就業規則類の見直しは実態に合わせ運用確認も
就業規則類は決め事(文書)と運用方法の見直しが重要 就業規則類は社内ルールとして重要な文書なことに間違いありませんが、就業規則類の見直しするにあたり、今まで5 ...
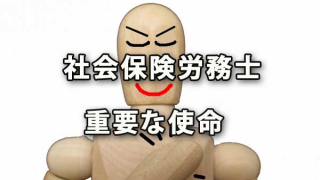
社会保険労務士の重要な使命とは
社会保険労務士の使命について 社会保険労務士の使命について、一般的にマーケットから期待されていることも知りたくて、ChatGPTさんに伺ってみました。 「社 ...

連続勤務は最大何日まで認められているか
連続勤務は最大6日? 7日? 12日? 24日? 人手不足に直面している企業では、長時間労働や休日出勤が発生しやすく、従業員に負荷がかかっているケースも少なく ...
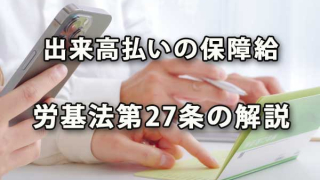
出来高払いの保障給(労基法27条)の解説
最近出来高払いの質問が多くなってきた 労働基準法第27条は以下の通り定められています。 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間 ...
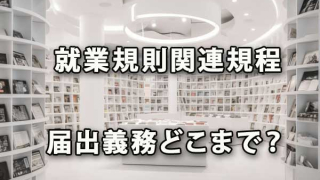
就業規則関連規程はどこまで労働基準監督署に届出義務があるか
莫大な文書体系で就業規則関連規程をどこまで届出か 就業規則の見直しについては、各社抜かりが無いものと察します。当事務所もお客さんに督促される始末で、なかなか仕 ...
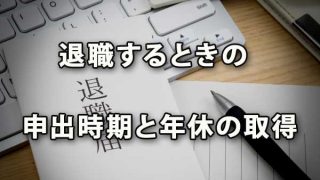
退職の申出時期と残期間、有給取得と認定の注意点
退職時の申出時季と年休 年度末は転職などにより退職者が発生しやすい時期です。従業員が退職する際に、退職の申出時期や年次有給休暇(以下、「年休」という)の取扱い ...
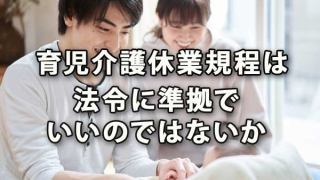
育児介護休業規程は法令に準拠でいいのではないか
あまりにも難解になりすぎた「育児介護休業法」 今年2022年10月に育児介護休業法の改正が予定されており、新たに盛り込まれる出生時育児休業(産後パパ育休)をは ...

2020年4月法改正-入社時の身元保証契約見直しを
2020年4月の民法改正に伴い入社時「身元保証書」に変更が 新入社員が入社する際、企業によって様々な提出書類を定めているものと思いますが、企業が必要書類として ...
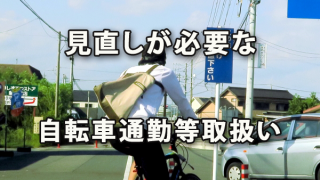
全国的な自転車保険加入義務化に伴い、要見直しの自転車通勤等取扱い
都道府県条例で自転車損害賠償保険等への加入義務が広がっている 健康増進等を目的として、自転車通勤をする人が増える一方で、条例で自転車利用中の対人事故の賠償に備 ...
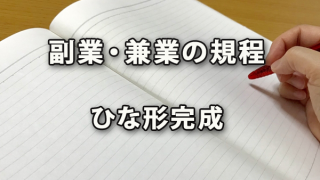
「副業・兼業に関する規程」のひな形完成
最近めっきり副業・兼業への対応問い合わせが多い 厚生労働省は2017年11月20日、「モデル就業規則」のうち、副業・兼業に関する規程の改定案提示され、2018 ...
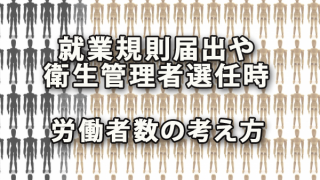
就業規則届出や衛生管理者選任時の労働者数考え方
事業場や企業を単位とした労働者数にて要求事項がある 労働基準法をはじめとした法令では、事業場を単位とした労働者数によって、就業規則の作成・届出が求められたり、 ...
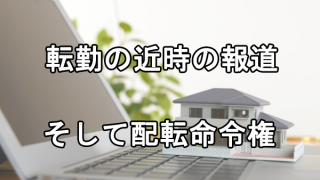
転勤をめぐる近時の報道と、配転命令権
AIG損保、転勤を廃止 AIG損害保険が、転勤の多い保険業界では珍しく、転勤を原則として廃止したと報道されました。 一般に「転勤のある社員」と「地域限定社員 ...

従業員への「損害賠償請求」注意点(業務中ミスの損害
会社から従業員への損害賠償請求は可能 先般、運送業のお客さんから従業員が2カ月で3回も事故を起こしてしまい、あまりに酷いので、自動車保険の対物保険免責額と来年 ...
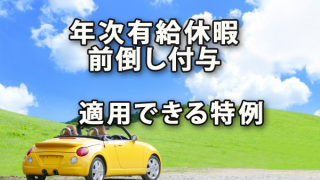
年次有給休暇を前倒しで付与した場合に適用できる特例
2019年4月に働き方改革関連法が施行されたことにより、年5日の年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得が企業に義務づけられました。 これにより企業はこの ...