2025年4月スタートの出生後休業支援給付金

「出生後休業支援給付金」の概要
雇用保険法の改正により、2025年4月から2つの新しい給付金制度が創設されます。
そのうちのひとつ、「出生後休業支援給付金」は、共働きや共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間において両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、最大で28日間、給付が受けられるという仕組みです。
育児休業を取得すると、一定の要件を満たした従業員(雇用保険の被保険者)は所得の補てんとして出生時育児休業給付金または育児休業給付金を受給することができます。ただし、通常、育児休業を取得する前と比較して手取額は低下することから、より高い補てんとすることを目的として、2025年4月から出生後休業支援給付金が創設されます。
この「出生後休業支援給付金」の制度や実務手続きに関する資料が、2025年1月17日に厚生労働省のホームページで公開されました。制度の枠組みとしては既存の育児休業給付金と似ている部分が多いのですが、要件や添付書類などのルールは従来の制度よりも複雑です。特に実務上注意しなければならないポイントを確認します。
「出生後休業支援給付金」の支給額
支給額は、原則として育児休業を開始する前6ヶ月に支払われた賃金の13%相当額です。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の給付率67%とあわせると、給付率が80%となり、手取りの10割相当額が支給される仕組みとなっています。
支給申請手続は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うことになります。
育児休業を取得する従業員の中には、配偶者が専業主婦(夫)であったり、ひとり親として育児をしていたりすることもあります。このように配偶者が育児休業を取得していない場合も、出生後休業支援給付金が支給されることがあります。その際には、配偶者の状況に応じた申告書や添付書類の提出が求められます。
「出生後休業支援給付金」の支給要件
「出生後休業支援給付金」の支給要件は以下のようになっています。1.2.をいずれも満たした場合に給付金の対象となります。
被保険者本人と配偶者の育休取得状況等を確認する必要があるというのがポイントです。また、2025年4月1日をまたいで育休を取得している場合の取扱いや、配偶者の育休取得を要件としないケースについても確認します。
- 被保険者が、対象期間(※1)に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
- 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(※2)に該当していること。
※1 対象期間
- 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
- 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。
- <point>
2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、下線部分を「2025年4月1日」と読み替えて要件を確認します。
※2 配偶者の育児休業を要件としない場合
子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。
なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4、5、6、のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
- 配偶者がいない
配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。 - 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など)が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。
被保険者が女性の場合や子が養子の場合は、上記のケースに該当するか確認したうえで、該当した場合はそのケースごとに定められた確認書類を添付することになります。(例えば、1の場合は、戸籍謄(抄)本(抄本の場合は被保険者本人のもの)及び世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等)

支給申請の実務
「出生後休業支援給付金」の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うことになります。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請する必要があります。
従来の育児休業給付金よりも制度が複雑になっていますので、手続きを行う際は、厚生労働省が公開した手引き『育児休業等給付の内容と支給申請手続』の内容をよく確認したいところです。
参考リンク
厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


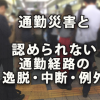
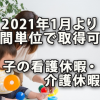
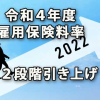
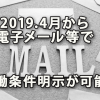
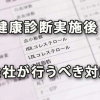
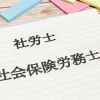

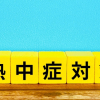


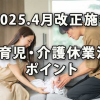


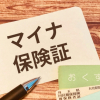
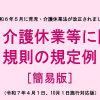



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません