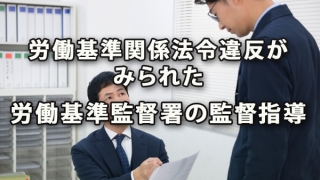
7割で労働基準関係法令違反がみられた労基準監督署の指導
長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の結果 過重労働対策の重要性が高まっており、労働基準監督署においてもその監督指導が積極的に行われています。 先日、 ...
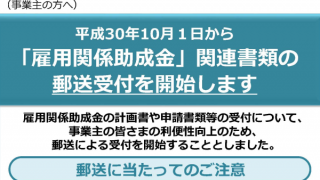
2018年10月1日より雇用関係助成金の郵送受付開始
窓口に出向いて書類を提出・申請が原則から郵送可能に 厚生労働省が管轄となる雇用関係の助成金は、申請先の窓口に出向いて書類を提出、申請することが原則でしたが、提 ...
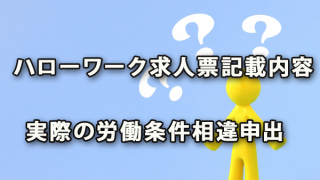
ハローワーク求人票内容と実際の労働条件相違の申出状況
求人票記載内容と実際の労働条件相違に係る申出等公表 厚生労働省は、平成29年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を ...
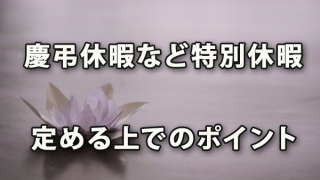
慶弔休暇など特別休暇のルールを定める上でのポイント
働き方改革関連法において、2019年4月以降、年次有給休暇(以下「年休」という)の取得義務化が行われますが、多くの会社では、この年休のほかにも従業員の慶弔が生 ...
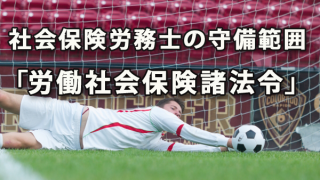
社会保険労務士の業務範囲の「労働社会保険諸法令」
社会保険労務士が扱う法令等は59 「社会保険労務士さんの扱う法律はどのくらいありますか」と問われ、正確に回答できなかったので、改めて「社会保険労務士法」を見返 ...

個別労働紛争の種は「いじめ・嫌がらせ」がトップ
個別労働紛争解決制度とは 会社と労働者との間の労働条件や職場環境をめぐるトラブルを防止・解決する制度のひとつとして、「個別労働紛争解決制度」があります。 こ ...
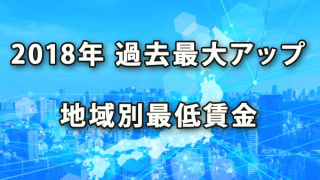
2018度も大幅の過去最大アップとなった地域別最低賃金
平成30年(2018年)度の地域別最低賃金は過去最大アップ全国平均874円 最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業はその額以上の賃 ...

半数程度に留まるマタハラ防止対策実施企業
ハラスメントの防止に関する取組み状況 最近、ハラスメントの問題がメディアを騒がせており、多くの企業においてハラスメント研修が実施されるなど、防止に向けた取組み ...

66歳以上まで働ける企業の割合に関する調査結果
66歳以上まで働ける企業の割合が増加 厚生労働省が公表した労働市場分析レポート「希望者全員が66歳以上まで働ける企業の割合について」によれば、従業員31人以上 ...

厚労省が無料利用サテライトオフィス開設~利用企業募集中
「テレワーク」利用可サテライトオフィスを8か所設置 厚生労働省では、「テレワーク」を行うときに無料で利用できる「サテライトオフィス」を、埼玉県、千葉県、東京都 ...
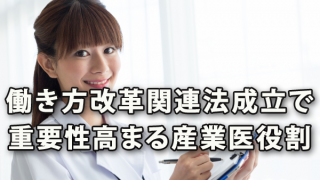
働き方改革関連法の成立により重要性が高まる産業医の役割
改正労働安全衛生法成立で産業医と産業保健の機能強化 働き方改革関連法の中で改正労働安全衛生法が成立したことにより、産業医と産業保健の機能が強化されることとなり ...
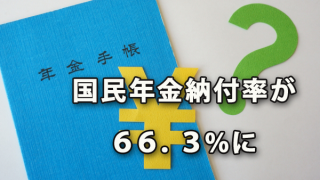
国民年金納付率66.3%に(平成29年度
国民年金被保険者の動向 国民年金保険料を納める必要があるのは、自営業者、学生等の第1号被保険者ですが、その動向を見ると、厚生年金保険(民間会社の)被保険者数の ...
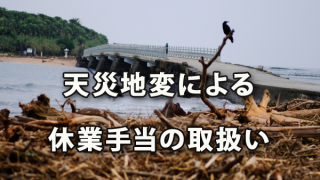
天災地変により従業員を休業させる場合の休業手当の取扱い
休業手当の基本的な考え方と天災地変の場合の取扱い 今年は地震や豪雨などの災害が頻発していますが、こうした天災地変により会社を休業せざるを得ないケースがあります ...
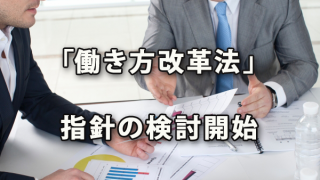
「働き方改革法」省令・指針の検討始まる
労政審の労働条件分科会で議論開始 2018年6月29日に働き方改革関連法が成立したことを受け、必要な省令や指針などについての議論が2018年7月10日、労働政 ...
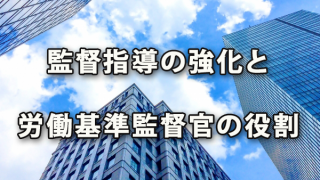
働き方改革関連法にて予想される監督指導強化と労働基準監督官役割
時間外労働の上限規制等に伴う監督指導等の強化を予想 2018年6月29日に成立した働き方改革関連法において、時間外労働の上限規制等が設けられ、2019年4月以 ...
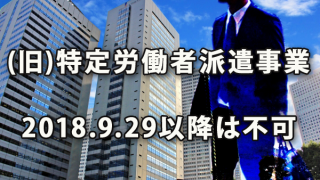
「(旧)特定労働者派遣事業」は2018.9.29以降は不可に
労働者派遣事業は「許可制」に一本化されています 労働者派遣事業は、改正前の「(旧)特定労働者派遣事業」を行っている場合、「許可制」への一本化に伴う経過措置が終 ...
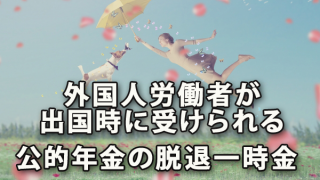
外国人労働者が出国時に受け取ることのできる公的年金の脱退一時金
年金保険料掛け捨て防止のための脱退一時金 日本に住む外国人労働者は、原則として国民年金や厚生年金に加入する義務がありますが、短期間でその資格を喪失して日本から ...
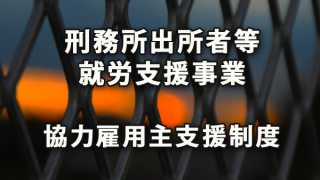
「刑務所出所者等就労支援事業」と協力雇用主の支援制度
「刑務所出所者等就労支援事業」の報告書公表 厚生労働省から、刑務所出所者等に職業相談や職業紹介等を行う「刑務所出所者等就労支援事業」についての報告書(「再出発 ...
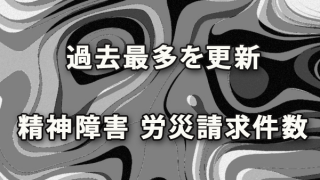
過去最多を更新した精神障害による労災請求件数
平成29年度の労災請求状況に関する集計結果より 長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷がかかり、従業員が脳・心臓疾患や精神障害を発症するケースが多くの企 ...

長時間労働はここ10年でどのくらい減ったのか?
月240時間以上の長時間労働、10年で減少 月に240時間以上の長時間労働をしている人が、この10年間で減少したことが、東京大学社会科学研究所の石田浩教授らの ...