
インフルエンザ予防の重要性とその効果
インフルエンザ予防で備える冬の健康管理 インフルエンザの流行が近づいてきました。。毎年多くの方が感染し、時には重症化するケースもあるインフルエンザ、この時期、 ...
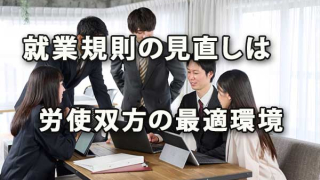
就業規則は変化に対応させ労使双方の最適環境を
公正な労働環境を確保するため時代の変化に合わせ適切に 就業規則は、雇用関係の基本ルールを定めた重要な文書です。近年、働き方改革や法改正の影響を受け、就業規則の ...

産後パパ育休申出を1ヶ月前までとする労使協定
2022年10月1日より産後パパ育休の制度がスタート 2022年10月1日より改正育児・介護休業法の第二段階目が施行され、産後パパ育休の制度がスタートします。 ...
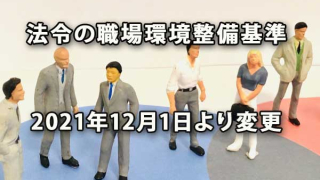
法令規定の職場環境整備基準が2021年12月1日より変更
事務所衛生基準規則や労働安全衛生規則改正 労務管理に関連する法令として、労働基準法や労働安全衛生法などがありますが、職場の環境や衛生等については事務所衛生基準 ...

iDeCoなど企業年金の対象者拡大~社会保障審議会で検討
中小企業向け企業年金拡大案2020年通常国会提出へ 厚生労働省は、社会保障審議会で中小企業向け企業年金制度の拡大に向けての案を示し、大筋で了承されました。来年 ...
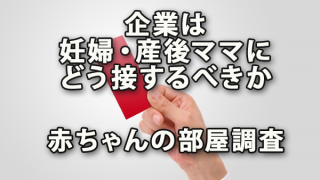
企業は妊婦・産後ママにどう接するべきか~赤ちゃんの部屋調査
3人に1人がマタハラを受けている パパとママのためのメディア「赤ちゃんの部屋」が、出産経験のある女性に「妊産婦の働き方と会社の取り組み」に関する調査を行いまし ...
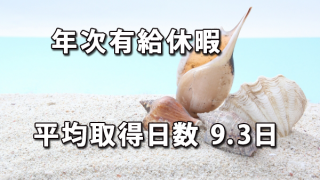
年次有給休暇の平均取得日数は9.3日
年休の取得状況と特別休暇制度の導入状況 来年4月より、年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される労働者に対して、年5日の取得義務がスタート ...
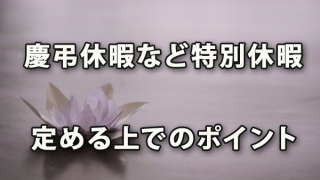
慶弔休暇など特別休暇のルールを定める上でのポイント
働き方改革関連法において、2019年4月以降、年次有給休暇(以下「年休」という)の取得義務化が行われますが、多くの会社では、この年休のほかにも従業員の慶弔が生 ...
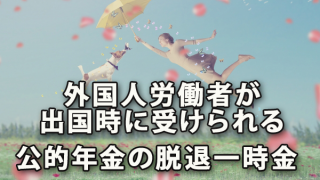
外国人労働者が出国時に受け取ることのできる公的年金の脱退一時金
年金保険料掛け捨て防止のための脱退一時金 日本に住む外国人労働者は、原則として国民年金や厚生年金に加入する義務がありますが、短期間でその資格を喪失して日本から ...
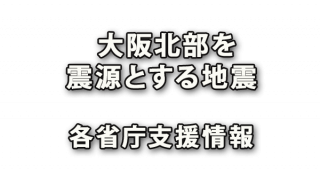
大阪北部を震源とする地震の各省庁支援情報
被災した皆さまには心からお見舞い申し上げます 2018年6月18日(月)午前7時58分ごろ、大阪府北部を震源とした地震が起き、大阪北部で震度6弱を観測したほか ...
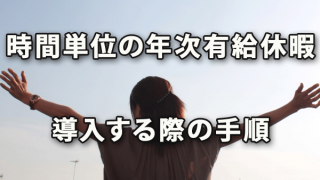
時間単位の年次有給休暇を導入する際の手順
平成22年4月より時間単位年休取得も認められる 労働基準法では、勤続年数等に従い、一定の年次有給休暇(以下、「年休」という)を付与することを企業に義務付けてい ...
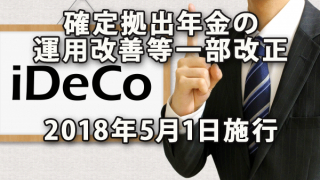
確定拠出年金の運用改善等の一部改正 2018年5月1日施行
平成28年6月に公布された「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」が定める確定拠出年金における運用の改善、中小企業向けの対策、年金制度間でのポータビリティ拡充 ...
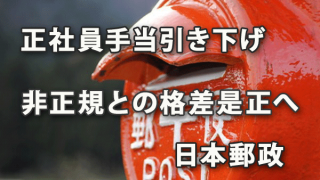
正社員の手当引き下げで非正規との格差是正へ~日本郵政
「同一労働同一賃金」実現へ正社員の手当引き下げ 日本郵政グループが、正社員のうち約5,000人の住居手当を今年10月に廃止するということです。この手当はこれま ...

手当等を活用して、従業員に会社の近くに住んでもらう試み
「引っ越し難民」発生中 今年は、希望のタイミングで引っ越しができない「引っ越し難民」が発生しているという報道が続いています。 もともと3~4月は、会社の転勤 ...
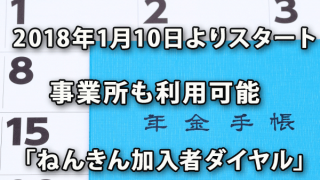
2018年1月開始の「ねんきん加入者ダイヤル」
「ねんきん加入者ダイヤル」は事業所も利用可能 日本年金機構では、年金事務所での対面での年金相談のほか、電話での相談も受け付けていますが、今月10日より、新たに ...
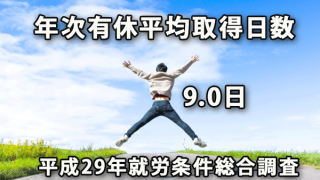
年次有休平均取得日数は9.0日(平成29年就労条件総合調査)
就職・転職で休暇を重視する傾向が高まっている 就職・転職する上で、休暇の取りやすさを重視する傾向が高まっています。 深刻な人材不足時代において安定的に人材を ...

有給休暇取得に関する動向とキッズウィークへの対応
◆10月は取得促進期間 厚生労働省は10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし、広報活動を行っています。企業において、翌年度の年次有給休暇の計画づくりを行う時期が ...
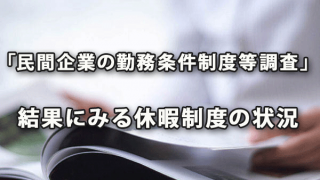
「民間企業の勤務条件制度等調査」の結果にみる休暇制度の状況
◆休暇等関する基礎資料 「民間企業の勤務条件制度等調査」は、人事院が、国家公務員の勤務条件等を検討するにあたっての基礎資料を得ることを目的として、民間企業の労 ...
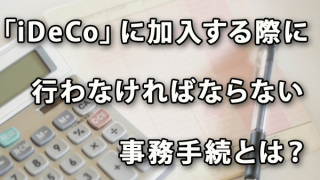
従業員が「iDeCo」に加入する際に事業主が行わなければならない事務手続とは?
◆改正を契機に加入者数が増加 今年1月からの改正確定拠出年金法の施行により、個人型確定拠出年金(通称:iDeCo)は、基本的に20歳以上60歳未満のすべての方 ...
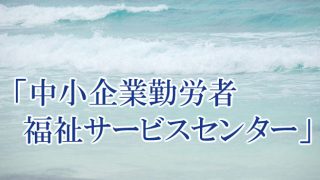
福利厚生充実のために活用を検討したい「中小企業勤労者福祉サービスセンター」
「福利厚生の充実」が与える好影響 昨今の人材難への対応策の1つとして、社員のモチベーションや満足度を向上させて会社への定着を図ったり、採用の際のアピールポイン ...