出生後休業支援給付・育児時短就業給付の経過措置

2025年4月1日前に育児休業等取得の措置
2025年4月から、雇用保険の新たな給付制度として「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」の仕組みがスタートします。
両制度に経過措置が設けられていますが、経過措置要件に該当すれば、施行日の2025年4月1日以前に育児休業を取得している場合や、時短勤務を開始している場合にも給付金を受け取ることができます。
やや複雑な仕組みではありますが、機会損失を起こさないためにもしっかりと理解しておきたいところです。
1.出生後休業支援給付の経過措置
出生後休業支援給付は、子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に受給できる給付金です。
この給付金には以下のような経過措置が設けられています。
- 被保険者が、対象期間(父親は、子の出生後8週間以内。産後休業をした母親は、子の出生後16週間以内)に通算14日以上の出生後休業をしたこと
※施行日前(2025年4月1日)から引き続き育児休業または産後パパ育休をしている場合、施行日から出生後休業を開始したものとして取り扱います。そのため、施行日以後の対象期間に、出生後休業が14日以上必要です。 - 被保険者の配偶者が、子の出生後8週間以内に通算14日以上の出生後休業をしたこと
※施行日前に取得した育児休業、産後パパ育休も対象となります。
ただ、この文章だけではイメージがしづらいので、具体的な年月日を用いて、受給できる条件を整理すると以下のようになります。下線部の出産日が受給対象となるかどうかの分岐点になるため、この日付をもって対象者を確認するとよいでしょう。
1)父親・母親ともに受給できる場合
- 母親が2025年2月17日以降に出産し、産後休業に続いて育児休業を14日以上取得している。
- 父親が2025年4月1日以降に育児休業または産後パパ育休を14日以上取得している。
2)母親のみ受給できる場合(1)
- 母親が2025年2月17日以降に出産し、産後休業に続いて育児休業を14日以上取得している。
- 父親が2025年4月1日以降に育児休業または産後パパ育休を14日以上取得していない。
3)母親のみが受給できる場合(2)
- 母親が2024年12月23日以降に出産し、産後休業に続いて2025年4月1日以降に育児休業を14日以上取得している。
- 父親が母親の産後休業中に育児休業または産後パパ育休を14日以上取得している。
2.育児時短就業給付の経過措置
育児時短就業給付は、2歳未満の子を養育するために育児時短就業をする場合に受給できる給付金です。
この給付金を受給できるのは、施行日(2025年4月1日)以降に時短就業を開始した者となっていますが、こちらも経過措置が設けられており、施行日前から引き続き育児時短就業をしている場合は施行日に育児時短就業を開始したものと取り扱います 。
このほかにも詳細な取り扱いが定められていますが、具体的な年月日を用いて整理すると以下のようになります。
1)2025年3月17日以前に、育児休業から復帰して引き続き育児時短勤務を開始した場合
(例:2025年3月17日に育休から復帰し、同日から育児時短勤務を開始した場合)
- 施行日(2025年4月1日)から遡って、みなし被保険者期間・賃金日額を確認・算定する。
2)2025年3月18日以降に、育児休業から復帰して引き続き育児時短勤務を開始した場合
(例:2025年3月18日に育休から復帰し、同日から育児時短勤務を開始した場合)
- みなし被保険者期間の確認は要さず、育児休業給付に係る休業開始時賃金日額を賃金日額とする。
3)2025年3月31日以前に、育児時短勤務を開始した場合(育児休業から連続しないとき)
(例:それまでは通常勤務だったが、2025年3月18日から育児時短勤務を開始した場合)
- 施行日(2025年4月1日)から遡って、みなし被保険者期間・賃金日額を確認・算定する。
いずれの給付金についてもやや複雑な経過措置が設けられていますので、具体的な日付を確認したうえで、給付金の対象となるかどうか判断します。
参考リンク
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年2月5日以降)」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


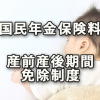


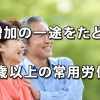


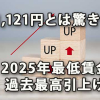
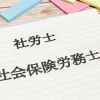

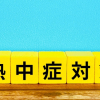


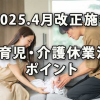


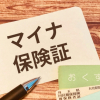
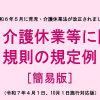
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません