どうなる物流2024年問題(ドライバー時間外労働上限規制の諸問題

物流の2024年問題とは
物流の2024年問題は、2024年4月1日以降、トラックドライバーの時間外労働の上限規制により発生する諸問題です。
当事務所にも運送業界から随分と問い合わせが多くなってきました。どうしたら良いのでしょうか。
以前より物流業界での課題であった、トラックドライバーの長時間労働の改善を目指し、自動車運転業務の年間の時間外労働時間上限が1,176時間から、2024年4月1日以降は960時間になります。
また、これまでは時間外労働の給与の割増率が25%だったのに対して、改正後は月60時間を超える分には50%以上に引き上げられます。
しかし、次のような課題が懸念されており、これを「2024年問題」と呼びます。
参考:公益社団法人全日本トラック協会「トラック運送業界の2024年問題について」
物流にかかわる企業の仕組み改善が必要になる
2024年以降、運送業や建設業などに時間外労働の上限規制が適用され、た残業時間が改正前より少なく制限されるため、物流にかかわる企業は交代制を取り入れる、業務効率化のために新たなシステムを導入するなど、これまでの物流の仕事のあり方や仕組みを改善するための取り組みが必要になります。
荷主や一般顧客の意識改革も必要になる
荷主から過積載を求められるケースもあるようです。厚生労働省では荷主側に改善を働きかけるとしています。
Amazonなどが随分と運賃が安いようですが、物流にもコストがかかるということを、荷主も、一般の顧客側も認識する必要があります。一人ひとりが物流には適正コストがかかるということを理解して欲しいものです。
2024年問題に向けた取り組み
これらの2024年問題に対応するために、政府や企業が様々な取組みを推奨しています。絵に描いた餅にならなければいいのですが…
以下はそのキーワードです。
- 働きやすい職場環境の整備
- 労働生産性の向上
- IT導入による効率化
2024年4月から適用となるトラック運転者の時間外労働の上限と改善基準告示
上述の通り2024年4月1日より、自動車運転業務、建設事業、医師について、時間外労働の上限規制が適用となり、併せて自動者運転業務に従事するトラック運転者、バス運転者、タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が2022年12月23日に改正されました。
2024年4月1日より施行されるトラック運転者に関する改正内容について解説します。
1)時間外労働の上限
トラック運転者について、特別条項付き36協定を締結する場合、年間の時間外労働の上限が年960時間となります。なお、この960時間には法定休日労働の時間数は含みません。ただし、一般企業等ですでに適用されている以下の2つについては適用されません。
- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで
そのため、1ヶ月の上限については規定がありませんが、例えばある月の時間外労働が100時間となった場合、他の月の時間外労働を削減すること等により、年960時間を超えないようにする必要があります。
2)改善基準告示
トラック運転者の改善基準告示が改正され、以下のようになります。
- 1年の拘束時間
3,516時間 ⇒ 原則:3,300時間(最大:3,400時間) - 1ヶ月の拘束時間
原則:293時間(最大:320時間)⇒ 原則:284時間(最大:310時間) - 1日の休息期間
継続8時間 ⇒ 継続11時間を基本とし、継続9時間を下回らない
この他、改正はありませんが、1日の拘束時間や運転時間など様々な基準が設けられています。
3)労働局に編成された「荷主対策チーム」
厚生労働省では、上記の改善基準告示を広く周知するために、「荷主特別対策チーム」が編成されています。この「荷主特別対策チーム」の活動として、トラック運転者の長時間労働の是正のため、発着荷主等に対して、長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請と、その改善に向けた働きかけが行われることになっています。
そのため、長時間の荷待ちに関する情報収集として、厚生労働省ホームページに、以下のような「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」が新設されており、発着荷主等が長時間の荷待ちを発生させていると疑われる事案などの情報を収集し、その情報を基に、労働基準監督署が要請等を行うとしています。
長時間の荷待ちに関する情報メール窓口
厚生労働省:長時間の荷待ちに関する情報メール窓口
2024年4月1日の施行まで1年余りです。自動車運転者を雇用するトラック運送業等は、時間外労働時間の削減に向けた取組を行うとともに、荷主の企業もトラック運送業に対する対応が適切なものになっているか考える必要があります。
参考リンク
厚生労働省:「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」
厚生労働省:「改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました」
(参考記事)https://www.yomiuri.co.jp/national/20221223-OYT1T50464/
読売新聞オンライン 2022/12/24トラック運転手、疲労満載…脳・心疾患での労災認定は全労働者の3割
トラック運転手らの長時間労働が常態化している。2021年度には脳や心臓疾患で労災認定を受けた全労働者の3割を占め、厚生労働省は23日、運転手の労働基準を25年ぶりに改正し、長時間労働の是正策を強化した。ただ、賃金が低く抑えられているという実態もあり、専門家は「労働環境を変えないと物流を維持できない」と警鐘を鳴らす。
長い拘束時間・人手不足
「明日は我が身」
「身近な人が次々に倒れ、『明日は我が身』と思った」。今年7月まで約20年間、トラック運転手として働いた埼玉県の男性(50)は振り返る。
関東地方でいくつかの運送会社に勤め、全国に食品や家電を運んだ。拘束時間は業種ごとに国が定め、トラック運転手の場合は月に原則293時間だが、450時間を超えることも珍しくなかった。納品は朝が多く、夜通しで走って昼間に運転席後ろの仮眠スペースで横になっても、実際に眠れるのは4~5時間。パーキングエリアでラーメンをすすり、運転中に大福で小腹を満たしていると、糖尿病も患った。
この間に、脳 梗塞 などで5人の同僚が倒れ、2人が亡くなった。給料も当初は手取りで40万円を超えたが、運送業の過当競争を受けて20万円台まで落ちた。男性は「体力の限界だった。労力に見合う給料も得られなかった」と話す。
全業種平均の10・3倍
厚生労働省によると、2021年度に国内で企業や官公庁などに雇用されている労働者は6013万人で、脳・心臓疾患での労災認定は172件あった。業種別の内訳でみると、トラック運転手ら190万人が従事する「道路貨物運送業」が最多の56件で全体の32・5%を占め、雇用者数に対する認定の割合は、全業種平均の10・3倍だ。比較のできる09年度以降、この業種は常に最多となっている。
背景には、トラック運転手らの過酷な労働環境がある。長距離運行が多い大型トラックの運転手の労働時間は、全産業平均(175時間)より2割長い月212時間だ。過酷な労働環境を敬遠して新規就労者は少なく、平均年齢は50歳に近い。
こうした状況を改善するため、厚労省は23日、トラック運転手らの労働基準を定めた告示を改めた。改正は1997年以来。2024年4月から適用される新基準では、月の拘束時間を9時間減の原則284時間とし、終業から次の始業までの間隔(勤務間インターバル)も延ばす。違反が確認されれば、国土交通省が事業者に対し、車両使用停止などの行政処分を行う。
荷主も改革必要
ただ、規制が強化されても、環境改善につながるかは不透明だ。都内の運送会社幹部は「運転手の労働環境改善には、荷主の意識改革も必要だ」と指摘する。長時間拘束の背景には、荷主の元での積み下ろしの順番待ちが長時間に及んでいるという実態があるからだ。
1990年に運送業が免許制から許可制に規制緩和されてから事業者数が増え、業界は過当競争に陥っている。この幹部は「運転手を守るために荷主へ環境改善を訴えれば、他の業者に乗り換えられかねない」と打ち明ける。荷主から過積載を求められるケースもあり、厚労省は今後、企業に立ち入って調査を行う労働基準監督署を通じて情報を集め、荷主側に改善を働きかける。
立教大の首藤若菜教授(労使関係論)は「運転手の拘束時間の削減と賃上げは急務だが、そのためには運送料の値上げは避けられない。輸送費が上がることで物の値段にも影響が及ぶかもしれないが、流通を止めないためには、荷主や消費者も負担を理解する必要がある」と指摘している。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
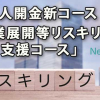

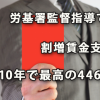
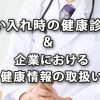
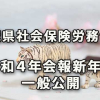
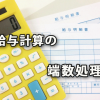
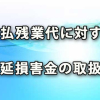
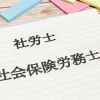

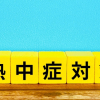




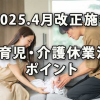


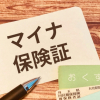
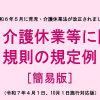



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません