雇用保険業務等のマイナンバー対応Q&A公表(18.4.11
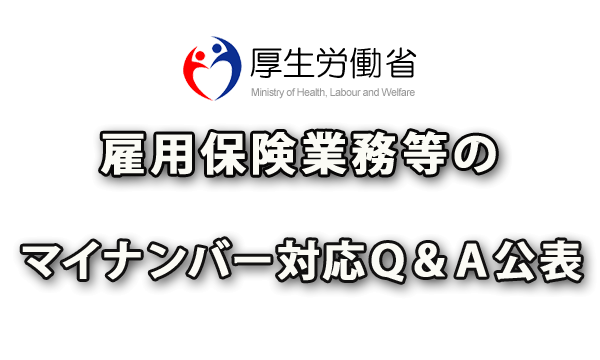
いよいよ来月(平成30年5月)より、雇用保険の届出等でマイナンバーを記載すべき届出等においてマイナンバーの記載がないときには、ハローワークでは処理を進めずに届出等が返戻されることになります。
これまでマイナンバーの届出を行ってこなかった企業では、届出等の進め方について検討されているかと思いますが、これに関連して厚生労働省から「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」が公開されました。
マイナンバーの記載について情報は得られていましたが、Q&Aには、マイナンバーが何らかの事情で記載できないときの対応についても記載されています。
「答」の中に「一定の確認等」という表現がありますが、それがどの程度のものになるか具体的な内容が分かりません。今後、更に具体的かつ詳細な内容が出てくることと予想しますが、まず全部で17項目あるQ&Aはに目を通しておきたいものです。
以下は、厚生労働省で公開している「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度対応Q&A」をテキスト起こししたものです。実務の参考になれば幸いです。
- 1. 雇用保険業務等におけるマイナンバー対応Q&Aの目次
- 2. 雇用保険業務等におけるマイナンバーの対応に係るQ&A内容(平成30年4月11日版)
- 2.1. 1.総論
- 2.1.1. Q1:雇用保険業務に番号制度がなぜ必要なのか。
- 2.1.2. Q2:雇用保険手続について、個人番号をハローワークに届け出る法的根拠は何か。
- 2.1.3. Q3:従業員の個人番号を届出しなかった場合に、ハローワークから督促等がされるのか。
- 2.1.4. Q4:H30年5月から個人番号の記載がない場合に届出等を返戻する法的根拠は何か。
- 2.1.5. Q5:番号制度の導入に伴い、雇用保険業務はどのように変わるのか。
- 2.1.6. Q6:個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出させるのではなく、個人番号の記載に一本化するべきではないか。
- 2.1.7. Q7:番号法で規定されている雇用保険業務に係る情報提供ネットワークにより照会・提供できるものにはどのようなものがあるか。
- 2.2. 2.留意事項
- 2.3. 3.記載を省略等できる場合
- 2.3.1. Q10:雇用保険手続について、手続の契機ごとに同一従業員の個人番号を重複して提出することになるのか。
- 2.3.2. Q11:資格取得届について、被保険者が以前に雇用されていた他の事業所が個人番号を届け出ている場合、個人番号の記載を省略できないのか。
- 2.3.3. Q12:以前に雇用していた被保険者(その際、当該事業所がハローワークに個人番号を届出済)がいったん離職した後、再度雇用することとなった。この場合であっても、資格取得届に再度個人番号の記載が必要か。
- 2.3.4. Q13:従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についてどのような取扱いとなるのか。
- 2.3.5. (参考)内閣府HPI社会保障・税番号制度1よくある質問(FAQ)Q&A4-2-6
- 2.3.6. Q14:従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。
- 2.3.7. Q15:従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、どのように対応すればよいか。
- 2.3.8. Q16:企業内の個人番号の取扱規程により、各種届出の際に個人番号の持ち出しができず、別途、個人番号登録・変更届で登録を行っている。このような届出が認められなくなるのか。
- 2.3.9. Q17:電子申請による届出等の場合、「マイナンバー届出済」である旨や本人が個人番号の届出を拒んでいること等を、どのように疎明すればよいか。
- 2.4. 参考リンク
- 2.5. 全投稿からの関連する記事:
- 2.1. 1.総論
雇用保険業務等におけるマイナンバー対応Q&Aの目次
- Q1:雇用保険業務に番号制度がなぜ必要なのか。
- Q2:雇用保険手続について、個人番号をハローワークに届け出る法的根拠は何か。
- Q3:従業員の個人番号を届出しなかった場合に、ハローワークから督促等がされるのか。
- Q4:H30年5月から個人番号の記載がない場合に届出等を返戻する法的根拠は何か。
- Q5:番号制度の導入に伴い、雇用保険業務はどのように変わるのか。
- Q6:個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出させるのではなく、個人番号の記載に一本化するべきではないか。
- Q7:番号法で規定されている雇用保険業務に係る情報提供ネットワークにより照会・提供できるものにはどのようなものがあるか。
- Q8:事業主が個人番号を提出する必要がある雇用保険手続はどのような手続があるか。
- Q9:個人番号の届出を郵送で行った場合に漏えい事故が発生するリスクがあるが、どのようにすれば良いか。
- Q10:雇用保険手続について、手続の契機ごとに同一従業員の個人番号を重複して提出することになるのか。
- Q11:資格取得届について、被保険者が以前に雇用されていた他の事業所が個人番号を届け出ている場合、個人番号の記載を省略できないのか。
- Q12:以前に雇用していた被保険者(その際、当該事業所がハローワークに個人番号を届出済)がいったん離職した後、再度雇用することとなった。この場合であっても、資格取得届に再度個人番号の記載が必要か。
- Q13:従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についてどのような取扱いとなるのか。
- Q14:従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。
- Q15:従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、どのように対応すればよいか。
- Q16:企業内の個人番号の取扱規程により、各種届出の際に個人番号の持ち出しができず、別途、個人番号登録・変更届で登録を行っている。このような届出が認められなくなるのか。
- Q17:電子申請による届出等の場合、「マイナンバー届出済」である旨や本人が個人番号の届出を拒んでいること等を、どのように疎明すればよいか。
雇用保険業務等におけるマイナンバーの対応に係るQ&A内容(平成30年4月11日版)
1.総論
Q1:雇用保険業務に番号制度がなぜ必要なのか。
(答)
個人番号は、その利用範囲が番号法において限定的に定められており、「社会保障、税及び災害対策に関する事務」でのみ利用できることとなっています。
雇用保険業務についても番号法第9条の別表第1において、雇用保険の資格取得・確認、給付の支給などに関する事務において個人番号を利用することが規定されています。
また、番号制度においては、「情報提供ネットワークシステム」(番号法第2条第14項)を用いて行政機関が符号をキーとして情報連携を行うことにより、国民が社会保障や税に関する諸手続を行う際の負担の軽減を図ることを目的としており、雇用保険業務においても番号制度の導入に伴い、行政事務の効率化や事業主の負担の軽減を図り、雇用保険制度の適正な運営に努めていくこととしています。
Q2:雇用保険手続について、個人番号をハローワークに届け出る法的根拠は何か。
(答)
事業主は、雇用保険法第7条及び第82条に係る雇用保険法施行規則の規定に基づき、雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届、雇用継続給付の申請などの手続を、公共職業安定所長に対して行うことと定められており、その際の様式は雇用保険法施行規則で定められています。
Q3:従業員の個人番号を届出しなかった場合に、ハローワークから督促等がされるのか。
(答)
事業主の個人番号の届出は法令で定められた義務ですので、御理解・御協力をお願いします。個人番号が未届の者に係る各種届出等については、返戻し、記載・添付いただいた上で届出等を受理します。
Q4:H30年5月から個人番号の記載がない場合に届出等を返戻する法的根拠は何か。
(答)
Q2の手続ごとの条文を根拠として、届出等書類の記載に不備があるものとして取り扱うものです。
Q5:番号制度の導入に伴い、雇用保険業務はどのように変わるのか。
(答)
番号制度の導入に伴い、雇用保険業務について、平成29年11月13日より、他の行政機関等との間で情報連携の本格運用が開始されており、効率的な業務運営を行うとともに国民の負担の軽減化を図ることとしています。
具体的には、
- 自治体がハローワークとの間で情報連携を行うことによる国民健康保険料(税)の減免手続における受給資格者証の添付書類の省略により申請者の手続の負担軽減
- ハローワークが自治体との間で情報連携を行うことによる介護休業給付における対象家族の住民票の写しの添付書類の省略により事業主等の手続の負担の軽減
などを行うこととしています。
Q6:個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出させるのではなく、個人番号の記載に一本化するべきではないか。
(答)
ハローワークにおいては、被保険者と個人番号との紐付けを行うための基本4情報(氏名、性別、生年月[、住所)のうち住所情報を有していないことから、従業員の個人番号を収集し、被保険者番号との紐付けを行う必要があります。
このため、個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出していただくこととしています。
Q7:番号法で規定されている雇用保険業務に係る情報提供ネットワークにより照会・提供できるものにはどのようなものがあるか。
(答)
情報提供ネットワークを活用した情報の照会・提供ができるのは、番号法別表第2に規定されている事項になります。
主なものとしては以下のとおりです。
- ハローワークが他の行政機関等に情報の照会ができる事務として、
- 未支給の失業等給付又は介護休業給付金に関する事務について、市町村に対して住民票関係の情報を照会すること(別表第2の77)
- 傷病手当の支給に関する事務について、健康保険における傷病手当金などの支給に関する情報を給付を行う行政機関等に対して照会すること(別表第2の78)
- 他の行政機関等がハローワークに情報の照会ができる事務として、
- 生活保護法による保護の決定や徴収金の徴収に関する事務について、都道府県等からハローワークに対して、失業等給付関係の情報を照会すること(別表第2の26)
- 非自発的失業者に係る保険料(税)の軽減の届出の確認の事務について、市町村からハローワークに対して、失業等給付関係の情報を照会すること(別表第2の27及び44)
2.留意事項
Q8:事業主が個人番号を提出する必要がある雇用保険手続はどのような手続があるか。
(答)
事業主が個人番号を提出する必要がある雇用保険手続は、次のとおりです。
- 個人番号が届出等様式の記載項目とされているもの
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(※)
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)
- 介護休業給付金支給申請書(※)
- 事業主が届出等に係る被保険者の個人番号をハローワークに未届の場合
届出等様式と合わせて個人番号登録・変更届を添付する必要があるもの(30年5月以降)- 雇用継続交流採用終了届
- 雇用保険被保険者転勤届
- 高年齢雇用継続給付支給申請書(2回目以降)(※)
- 育児休業給付金支給申請書(2回目以降)(※)
(※)原則として事業主を経由して提出していただくこととしていよすが、やむを得ない理由のため事業主を経由して提出できない場合には、本人が届出を行うことも可能です。
Q9:個人番号の届出を郵送で行った場合に漏えい事故が発生するリスクがあるが、どのようにすれば良いか。
(答)
個人番号については、厳重な管理が必要とされていますので、できるだけ電子申請により届け出ていただき、郵送による提出はご遠慮いただきますようお願いいたします。
電子申請の場合には、平成28年1月より、事業主が指定する者個人のマイナンバーカードを電子証明書として利用することが可能となっていますので、積極的な利用をお願いします。
なお、郵便での届出を行う場合は、漏えい、紛失等の事故を防止するため、安全な方策を講じる必要があり、電子媒体又は書類等を持ち出す際の安全な方策の例として、追跡可能な移送手段等が挙げられていますので、やむを得ず郵送により処理を行う場合には書留等の記録付郵便により、返信用封筒(書留等の記録付郵便によることとした場合の郵券を貼付の上、宛名を記載)を同封いただきますようお願いします。
3.記載を省略等できる場合
Q10:雇用保険手続について、手続の契機ごとに同一従業員の個人番号を重複して提出することになるのか。
(答)
雇用保険手続において雇用保険被保険者資格取得届等に個人番号を記載することは、雇用保険法令で定められているため、手続の契機ごとに個人番号を記載して当該届出を提出することが基本ですが、当該従業員を雇用する事業主からの他の契機に届け出られていることが確認できる場合には、事業主等が「マイナンバー届出済」と欄外等に疎明を行っていただくことにより、資格取得届を除き、これを受理することとしています。
この場合、事業主等が「マイナンバー届出済」と欄外等に疎明を行っていただく必要がありますが、個人番号又は上記の「マイナンバー届出済」の記載がない届出等を郵送等で受理した場合には、届出書上に疎明を求めることができないため、返戻させていただきます。
Q11:資格取得届について、被保険者が以前に雇用されていた他の事業所が個人番号を届け出ている場合、個人番号の記載を省略できないのか。
(答)
いったん離職し再就職までの間に個人番号の変更がある場合、これをハローワークが把握することはできず、再就職後の事業所における届出が必須であるため、雇用保険被保険者資格取得届での個人番号の記載の省略を行うことはできません。
Q12:以前に雇用していた被保険者(その際、当該事業所がハローワークに個人番号を届出済)がいったん離職した後、再度雇用することとなった。この場合であっても、資格取得届に再度個人番号の記載が必要か。
(答)
事業主は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令等において定められている保存期間等を経過した場合は、個人番号を速やかに削除又は廃止しなければならないとされています(例えば、給与所得者の扶養控除等申告書は7年間保管することとされている等、最長7年まで保管しているケースが考えられます)。
事業主が、以前の雇用関係に基づき当該者の個人番号を把握してハローワークに届け出ており、当該個人番号の変更がないことを確認の上、被保険者資格取得届に「マイナンバー届出済」の疎明を行う場合には、ハローワークにおいて、当該者の個人番号の届出が済んでいることを確認の上、これを受理することとしています。
Q13:従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についてどのような取扱いとなるのか。
(答)
雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めることとなります。仮に提供を拒否された場合には、ハローワークが一定の確認等をした上で受理することとしています。
(他にQ10、Q12、Q14、Q16参照。)
※個人番号の記載がないことのみをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。
その場合であっても、法令上定められた届出期限内(注)での届出をお願いしています。
注:届出期限
- 雇用保険被保険者資格取得届:雇用した日の属する月の翌月10日よで
- 雇用保険被保険者資格喪失届:離職日の翌々日から10日以内
(参考)内閣府HPI社会保障・税番号制度1よくある質問(FAQ)Q&A4-2-6
Q:税や社会保障の関係書類へのマイナンバーの記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの操供を拒んだ場合、どうすればいいですか。
A:社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、操供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の掛出先の機関の指示に従ってください。
Q14:従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。
(答)
雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届け出ることは法令で定められた義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただきますが、ハローワークが一定の確認等をした上で、受理することとしています。
Q15:従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、どのように対応すればよいか。
(答)
個人番号の提供が受けられなかった場合は、提供を求めた記録等を保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは、提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
Q16:企業内の個人番号の取扱規程により、各種届出の際に個人番号の持ち出しができず、別途、個人番号登録・変更届で登録を行っている。このような届出が認められなくなるのか。
(答)
各種届出等の際に個人番号未届の者に係る届出等については、当該届出等を返戻することを基本としていますが、事業所から「個人番号登録・変更届」による別途の個人番号の届出が確実に見込まれる場合には、個人番号届出期日の目処を確認の上、個人番号未届であっても、各種届出等を受理することとしています。
Q17:電子申請による届出等の場合、「マイナンバー届出済」である旨や本人が個人番号の届出を拒んでいること等を、どのように疎明すればよいか。
(答)
電子申請による届出等の場合、備考欄(備考欄が存在しない資格喪失届については社会保険労務士欄の直下のスペース欄)に「マイナンバー届出済」又は「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載していただくこととしています。
参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/2018QA.pdf
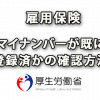





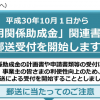
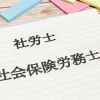

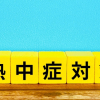




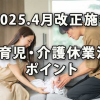


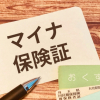
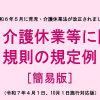



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません