「エイジフレンドリーガイドライン」高年齢労働者が安心して輝く職場へ

なぜ今、高年齢労働者の安全が重要なのか?
2020年3月16日に厚生労働省から公表された「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン)について、分かりやすくご紹介します。
このガイドラインは、高年齢労働者が生涯にわたり健康で安全に活躍できる職場環境を築くための、まさに新時代の指針となるものです。
近年、私たちの社会では高年齢労働者の就労が一層進んでいます。それに伴い、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者が占める割合が増加傾向にあり、平成30年には26.1%に達しました。
さらに、労働者千人当たりの労働災害件数(千人率)を見ると、25~29歳と比べて65~69歳の層では男性が2.0倍、女性が4.9倍と、高年層で相対的に高いことが示されています。
このような現状を踏まえ、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境を実現することが喫緊の課題となっているのです。
ここでいう「高年齢労働者」とは、具体的に何歳以上という定義は明記されていませんが、上記の統計データから「60歳以上の労働者」が主要な対象であり、特に65~69歳の層に注目した対策が求められていると読み取ることができます。
「エイジフレンドリーガイドライン」とは?
このガイドラインは、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防、健康づくりを推進するために、事業者と労働者それぞれに求められる具体的な取り組みを示しています。事業者と労働者がそれぞれの役割を理解し、連携して取り組むことが非常に重要だとされています。
事業者に求められる主な取り組み
事業者は、高年齢労働者の就労状況や業務内容の実情に応じて、国や関係団体等の支援も活用しながら、法令で義務付けられている事項に加えて、実施可能な高齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努めることが求められています。
具体的な取り組みは以下の5つの柱から成り立っています。
1. 安全衛生管理体制の確立等
- 経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当組織や担当者を明確にすること。
- 高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害のリスクアセスメント(危険源の洗い出しと優先順位付け)を実施すること。
- 「エイジアクション100」チェックリストの活用も有効です。
2. 職場環境の改善
- ハード面:
照度の確保、段差の解消、滑りやすい箇所の対策、補助機器(パワーアシストスーツ等)の導入など、身体機能の低下を補う設備・装置を導入すること。 - ソフト面:
短時間勤務、隔日勤務、交替制勤務などの勤務形態の工夫、ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢への配慮、定期的な休憩の導入など、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理を行うこと。
3. 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
- 健康診断や体力チェックにより、事業者と高年齢労働者双方が客観的に健康や体力の状況を把握すること。
- 体力チェックには、厚生労働省作成の「転倒等リスク評価セルフチェック票」などの活用が推奨されています。
4. 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
- 健康診断や体力チェックの結果に基づき、個々の高年齢労働者の健康と安全に適合する業務にマッチングさせること。
- 集団および個々の高年齢労働者を対象に、身体機能の維持向上に取り組むこと(運動指導、栄養指導、メンタルヘルスケアなど)。フレイルやロコモティブシンドロームの予防も意識します。
- 治療と仕事の両立支援も考慮すること。
5. 安全衛生教育
- 十分な時間をかけ、写真や図、映像など文字以外の情報も活用し、作業内容とそのリスクについて理解しやすい教育を実施すること。
- 再雇用や再就職等で経験のない業種や業務に従事する高年齢労働者には、特に丁寧な教育訓練を行うこと。
- 高年齢労働者自身が、自身の身体機能の低下が労働災害リスクにつながることを自覚し、体力維持や生活習慣改善の必要性を理解することが重要です。
労働者に求められる主な取り組み
高年齢労働者自身も、生涯にわたり健康で長く活躍するために、事業者が実施する労働災害防止対策に協力するとともに、自己の健康を守る努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組むことが必要です。
具体的な取り組みは以下の通りです。
健康状態や体力状況の客観的な把握と維持管理
- 自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や体力の維持管理に努めること。
- これは高齢になってから始めるのではなく、青年期や壮年期から取り組むことが重要です。
- 労働安全衛生法で定める定期健康診断を必ず受診し、対象とならない場合は地域の健康診断等(特定健康診査等)を受けるよう努めること。
- 事業者が行う体力チェック等には積極的に参加し、自身の体力水準を確認し、気づきを得ること。
体力維持と生活習慣の改善
- 日ごろから足腰を中心とした柔軟性や筋力を高めるためのストレッチや軽いスクワット運動などを取り入れ、基礎的な体力の維持と生活習慣の改善に取り組むこと。
- 各事業所の目的で行われているラジオ体操や転倒予防体操などの職場体操には積極的に参加すること。また、通勤時間や休憩時間にも簡単な運動をこまめに行うなど、自ら効果的と考える運動を積極的に取り入れること。
- 適正体重の維持、栄養バランスの取れた食事など、食習慣や食行動の改善に取り組むこと。
ヘルスリテラシーの向上
- 青年期・壮年期から健康に関する情報に関心を持ち、健康や医療に関する情報を入手、理解、評価、活用できる能力(ヘルスリテラシー)の向上に努めること。
労働災害リスクの認識
- 自身の身体機能の変化が労働災害リスクにつながる可能性を理解し、労使の協力のもと、具体的な取り組みを進めること。
国・関係団体等による支援も活用しよう
事業者が労働災害防止対策に取り組む際には、国や関係団体等による支援策を効果的に活用することが望ましいとされています。
具体的には、以下のような支援があります。
- 個別事業場に対するコンサルティング等の活用
- エイジフレンドリー補助金等の支援策の活用
- 中小企業や第三次産業における取組事例の活用
エイジフレンドリーガイドラインまとめ
「エイジフレンドリーガイドライン」は、高年齢労働者が増える現代において、誰もが安全に、そして長く活躍できる職場を実現するための重要な羅針盤です。事業者と労働者がそれぞれの役割を理解し、積極的に協力し合うことで、より良い職場環境を築いていくことができます。
このガイドラインが広く活用され、年齢に関わらず誰もが安心して働ける社会が実現することを願っています。
参考リンク
厚生労働省:高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)公表
高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン概要(PDF)
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
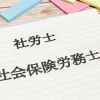
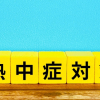

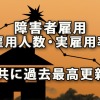
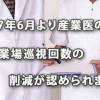
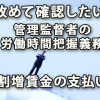




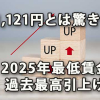





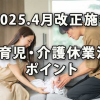


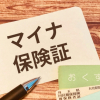
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません