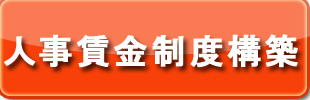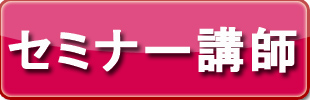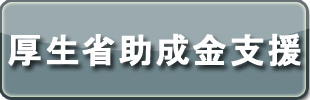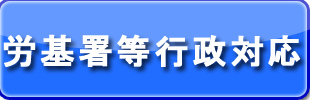作成日:2018年08月10日
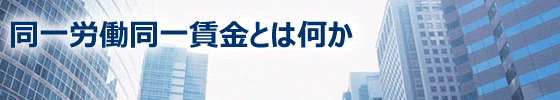
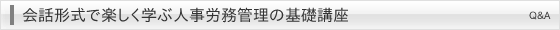
同一労働同一賃金に関する2つの注目される最高裁判所の判決(長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件)が、2018年6月1日に言い渡された。これらの判決を受け、会社としてどのような対応が必要なのか、社労士に相談することにした。
「木戸部長」
こんにちは。猛暑が続き、熱中症対策が必要不可欠ですね。
そうですね。体調管理を万全に行っておきたいところです。今日は、6月1日に同一労働同一賃金に関する2つの最高裁判決(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)が出たことから、この情報提供をしたいと思って伺いました。
「木戸部長」
新聞などでもとり上げられていましたね。社内でも同一労働同一賃金について、どのように対応していくのか話が出ていたところです。
同一労働同一賃金に関しては、2018年6月29日に働き方改革関連法が成立し、大企業は2020年4月1日から、中小企業は2021年4月1日から改正法が施行されます。
また「同一労働同一賃金ガイドライン案」が2016年12月に出されていますが、働き方改革関連法の成立に伴い、今後、年内を目処にガイドラインとして確定する予定になっています。
「木戸部長」
なるほど。ガイドラインが出てくるとなると、これも踏まえて対応していく必要がありますね。
はい。そこで今日は2つの最高裁判決を受けて、会社としてどのような対応が必要となるのかを解説しましょう。まず押さえておくべきポイントとしては、「同一労働同一賃金」とは何かという点です。
「木戸部長」
同一労働同一賃金とは、同じ業務をしていれば賃金も同じにしなければならないという意味ではないのでしょうか?
そのように理解している人が多くいますが、この意味での同一労働同一賃金を定めた法律はありません。働き方改革関連法が成立しましたがこの中にも規定されていません。法律で定められているのは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保であり、「均等待遇」と「均衡待遇」になります。
「均等待遇」とは、前提となる状況が同一であれば同一の待遇にすることを求めるものであり、「均衡待遇」とは、前提となる状況に違いがあればその違いに応じた待遇をすることを求めるものになります。
「木戸部長」
均等待遇が求められているのか、それとも均衡待遇が求められているのか、状況を確認した上で検討しなければならないということですね。この前提となる状況とはどのように考えるのでしょうか?
基本的には職務内容、職務内容・配置の変更範囲に違いがあるのかという状況を見ていくことになります。この職務内容とは業務内容、責任の程度のことであり、いわゆる非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の職務が正社員と比べてどのようになっているのかを確認していきます。
「木戸部長」
なるほど。責任の程度というのは、権限や役割の範囲に違いがあるのかという点をみていけばよいのでしょうか?
そうですね。そのほか、トラブル発生時や緊急時の対応、成果への期待の程度なども考えられます。
次に、職務内容・配置の変更範囲について、まず職務内容の変更範囲は職務が限定されているか、役割の変更があるかということであり、配置の変更範囲は、転勤や昇進、出向等が考えられます。
「木戸部長」
いろいろな要素から違いがあるのかをみていく必要がありそうですね。
当社では正社員、契約社員、パートタイマーの3つの雇用形態があり、それぞれで求める職務内容が異なり、また正社員には配置転換を行う可能性があります。均等待遇の方は問題がなさそうですが、均衡待遇の方が気がかりです。
確かに少なからず何らかの差はあるけれども、その差の程度が待遇の差とバランスが取れているかを判断するのは難しいですよね。実は、今回の最高裁判決では均衡待遇を争っており、この中で賃金項目の各手当を個別にみて、その手当の趣旨から不合理な点がないか判断がなされています。
「木戸部長」
なるほど。当社では、正社員に資格手当、家族手当、住居手当、通勤手当の4つの手当を支給していますが、契約社員とパートには通勤手当のみを支給しています。今後は、契約社員やパートタイマーにも資格手当、家族手当、住居手当を支給しなければならないということでしょうか?
必ずすべての手当について支給しなければならないということではなく、各手当の支給目的を明確にし、不合理とならないようにしていくことが求められます。例えばハマキョウレックス事件では、住宅手当を正社員のみに支給していることについて、正社員には転居を伴う配転が予定されていることから不合理ではないとしています。
会社としては、人材活用の仕組みの違いがあることから、住宅手当は正社員のみを対象としているなどの説明ができるのか、その他の手当についても説明ができるのか、説明ができなければ今後どのような対応をしていくか検討していく必要があります。
「木戸部長」
まずは全体を整理していくところからはじめる必要がありますね。
そうですね。進めていただく中で疑問点等がでてきましたら、お声がけください。
>>次回に続く
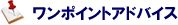
今回は、同一労働同一賃金とは何かについて解説しましたが、これに関する働き方改革関連法について補足しておきましょう。
現在、均等待遇、均衡待遇はパートタイム労働法と労働契約法の中で定められていますが、今後、労働契約法の中で定められていたものが、パートタイム労働法に組み込まれ、パートタイム労働法の対象に有期雇用労働者も含まれます。そして、法律も「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」になり、「パート・有期法」と呼ばれたりすることになるでしょう。
また、この同一労働同一賃金は、企業が直接雇用している人だけでなく、派遣労働者についても派遣法の中で求められ、派遣先の労働者との均等・均衡待遇か、一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかの対応が必要となります。この対応について、派遣元は企業規模に関わらず2020年4月より施行となります。そのため、派遣先(中小企業)では、自社の検討よりも先行して派遣元から派遣社員に関して相談される可能性があります。
参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
作成日:2018年08月10日
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
過去1年のバックナンバー
- 割増賃金の基礎から除外できる住宅手当の考え方 19.04.12
- 在宅勤務等の事業場外での働き方を検討する際のポイント 19.03.14
- ゴールデンウィークの10連休への対応を検討するポイント 19.02.14
- 36協定の特別条項を運用する際の注意点 19.01.13
- 在宅勤務等事業場外の働き方検討のポイント 18.12.14
- 副業・兼業を検討する際の留意点 18.11.11
- 企業に求められる自然災害対策(BCP) 18.10.12
- 改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金 18.09.15
- 同一労働同一賃金とは何か 18.08.10
- 従業員の個人情報を取扱う際の注意点 18.07.16
- ストレスチェックの実施と関連して活用できる助成金 18.06.14
- 平成30年度労働保険年度更新と確認したい高年齢被保険者の取扱い 18.05.10
- 締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否 18.04.12