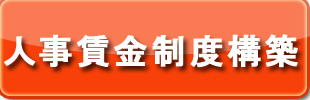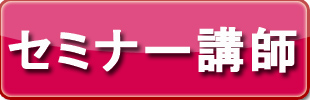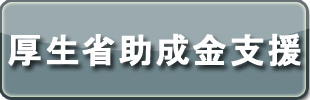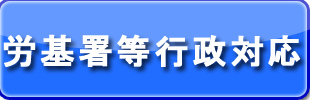作成日:2016年08月11日
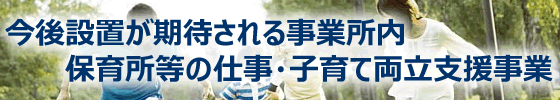
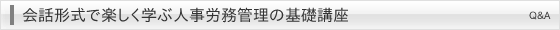
坂本工業では、小学校入学前の子どもを育てる従業員が増え、企業としてどのような子育て支援ができるかを検討することになった。その前提として、企業が負担している子ども・子育て拠出金について、確認をすることとした。
「木戸部長」
今年4月に子ども・子育て拠出金の拠出金率が0.15%から0.2%に引上げられましたね。他の社会保険の料率と比較して拠出金率が低いので、企業の負担としてはさほど大きく感じられませんが、そもそも子ども・子育て拠出金はどのようなことに利用されているのですか?
確かに、あまり周知がされていないので、そのような疑問を抱くかもしれませんね。この拠出金は、昨年度まで主に児童手当の財源として充てられてきました。そして、児童手当の他にも、放課後児童クラブや病気の子どもを保育する病児保育の事業費といった「地域子ども・子育て支援」にも充てられていましたが、これに加え、平成28年度からは「仕事・子育て両立支援事業」にも活用されることになっています。
「坂本社長」
今回、引上げられた拠出金率による財源は、新規の事業を中心に充てられるということですね。
そうです。この「仕事・子育て両立支援事業」ですが、メニューとしては、「企業主導型保育事業」や「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」があります。待機児童が多くいるため、政府としてはその受け皿として、企業が主導となって保育所を作ること等を奨励しています。また、これまでは厚生労働省が主導してきたベビーシッター派遣事業について、内閣府で実施することにし、補助内容を拡充しました。
「坂本社長」
なるほど、いろいろな制度があるのですね。まず、企業主導型保育事業ということは、これまで地方公共団体が主体となって整備されてきた保育所の設置や運営を企業が主導で行うということですね。
そうですね。これまでも事業所内保育所を作り、従業員の子育てを支援してきた企業がありますが、このような事業所内保育所ですと、開所時間を柔軟にできるなど、多様な就労形態に応じた保育サービスが考えられます。例えば、土曜日や日曜日にも出勤が求められる企業において、これらの曜日も開所する保育所を設置するといったイメージです。
「木戸部長」
なるほど。常態的に深夜勤務がある企業も同じことが言えそうですね。
はい。これまで事業所内保育所を設置し運営し続けることは、企業の費用負担が大きく、結果として利用者である従業員が負担する保育料も大きくなりがちでした。そのため、看護師等の人員確保が求められる医療機関等を中心に設置されてきましたが、今回の仕事・子育て両立支援事業の創設により、認可施設並みの助成が受けられ、利用者の負担も同等に設定することが可能となりました。
「坂本社長」
なるほど、確かに費用負担面が低減すると、企業としては設置を検討しやすくなりますね。
「木戸部長」
ところで、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業とは、どのようなものですか?
従業員がベビーシッターを利用した場合に、その利用料金の一部(または全部)を補助するものです。
「木戸部長」
ベビーシッターの利用にも補助が出るのですか!?
はい。ただし、いくつかの留意点があります。まずは補助の対象となるベビーシッター事業者は、事前に公益社団法人全国保育サービス協会(以下、「全国保育サービス協会」という)に申請をし、認定を受けておく必要があり、従業員はそのベビーシッター事業者を利用する契約を結ぶ必要があります。そして、企業がベビーシッターを利用したときに補助される割引券を全国保育サービス協会に申込み、それを従業員に渡しておくことになります。
「木戸部長」
そうですか。案外、複雑な仕組みですね。
そうですね。ただ、割引券の利用により割り引かれる金額は1日(1回)2,200円であり、ベビーシッターを利用する従業員にとっては、負担がかなり軽くなるのではないでしょうか。
「坂本社長」
確かに割引金額は大きいですね。企業としては、割引券を申込むだけでよいのですか?
企業としては、割引券利用手数料として割引券1枚につき中小事業は110円、大企業は220円を支払わなければなりません。なお、多胎児の場合には、割引金額等が異なりますので、詳細は内閣府や全国保育サービス協会のホームページで確認してください。
「坂本社長」
なるほど、承知しました。当社の従業員がどのような子育て支援を求めているかについては確認していませんが、一度、調査をしてみて、できることから進めていこうと思います。
そうですね。特に事業所内保育所の設置に関しては、継続的な利用が見込まれるかといったことも設置の判断になるかと思います。求められるものと企業ができることを調整しながら進めることがよいのでしょう。
>>次回に続く
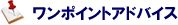
子ども・子育て拠出金率ですが、財政状況に応じて、今後、財政状況により0.25%までの中で拠出金率が変更になる可能性があります。どのようなことに利用されていくのか、注目しておきたいものです。
■参考リンク
内閣府「仕事・子育て両立支援事業・その他」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html
公益社団法人全国保育サービス協会「ベビーシッター派遣事業のご案内」
http://www.acsa.jp/htm/babysitter/index.htm
作成日:2016年08月11日
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
過去1年のバックナンバー
- 割増賃金の基礎から除外できる住宅手当の考え方 19.04.12
- 在宅勤務等の事業場外での働き方を検討する際のポイント 19.03.14
- ゴールデンウィークの10連休への対応を検討するポイント 19.02.14
- 36協定の特別条項を運用する際の注意点 19.01.13
- 在宅勤務等事業場外の働き方検討のポイント 18.12.14
- 副業・兼業を検討する際の留意点 18.11.11
- 企業に求められる自然災害対策(BCP) 18.10.12
- 改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金 18.09.15
- 同一労働同一賃金とは何か 18.08.10
- 従業員の個人情報を取扱う際の注意点 18.07.16
- ストレスチェックの実施と関連して活用できる助成金 18.06.14
- 平成30年度労働保険年度更新と確認したい高年齢被保険者の取扱い 18.05.10
- 締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否 18.04.12